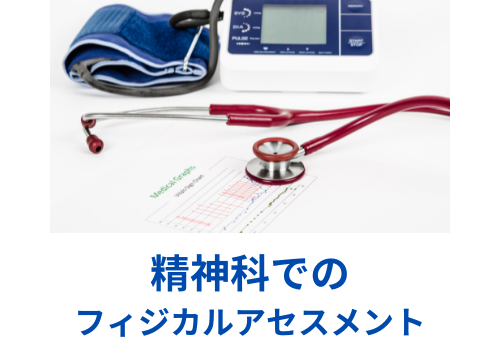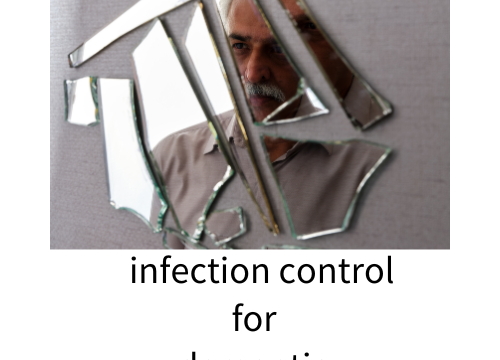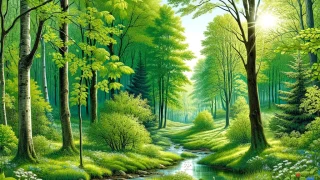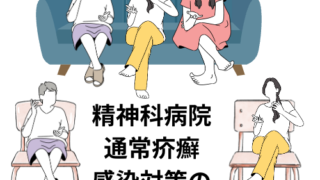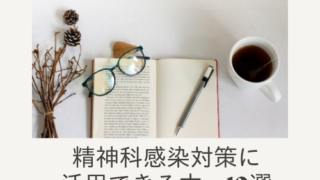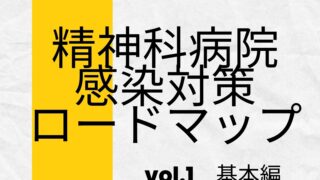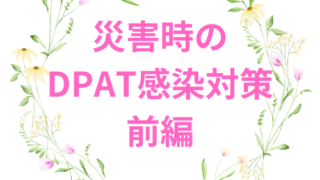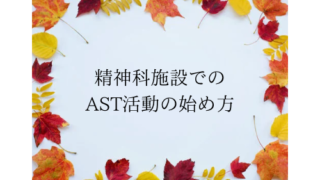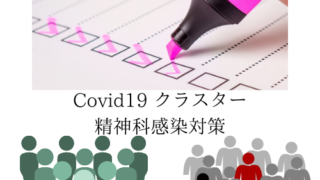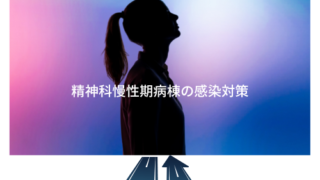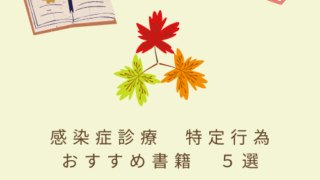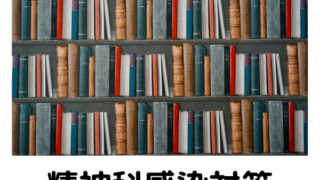認知症病棟で初めて働く看護師のあなたへ
お茶を提供するとむせてしまったり、唾液だけでもむせこんでしまう。
むせこんだ後に、脈拍数が上がり、熱が出て胸部レントゲン撮影を行うと肺炎となっているような認知症患者さんは多くないですか。
認知症者の誤嚥性肺炎対策を行うことで、肺炎を予防・早期発見し重症化を防ぐには
結論
認知症の進行状況を把握し、老化による臓器機能低下を理解して対策をとる
1)認知症患者の誤嚥性肺炎の特徴
・発症の2つのパターン
COVID19などのウイルス感染後や熱中症など体調の悪い日は誤嚥を起こす事がある。
嘔吐による胃内容物を嘔吐した際に誤嚥することもある
不顕性誤嚥:むせない誤嚥
知らないうちに細菌を含む唾液が気道に流入し発症する
2)既往歴に脳梗塞はないか確認する
大脳基底核に梗塞巣がある場合は、咳の反射、嚥下反射が低下するため注意が必要
脳梗塞👉基底核の血流低下👉黒漆線状態のドパミン低下👉サブスタンスPの低下👇
咳嗽反射・嚥下反射の低下 👉 嚥下困難 👉 肺炎
3)中枢神経抑制がある薬を内服していないか
抗不安薬・鎮静剤・睡眠薬の効果で誤嚥してしまう
4)口腔内が汚染している場合
口の中の細菌が増加し誤嚥のリスクが高まる
5)認知症重度時期
認知症の進行により、日常生活(食事・排泄・移動・清潔)が介助を要する場合
1)誤嚥性肺炎のある認知症者へのアセスメント
・全身状態の把握・評価
バイタルサイン 体温・脈拍・血圧・脈拍数・呼吸数
意識レベルの観察 グラスコーマスケール(GCS)
・認知症の臨床的ステージを医師と共有
2)胸部の聴診・視診・触診・食事場面の観察
| 聴診 | 胸部聴診:左右の呼吸音を聞く 気管支の狭窄音 肺複雑音
頸部聴診:嚥下音を聞く 飲み込む時のむせ 構音障害:パ・タ・カ・ラなどの発生状況 *背中側も必ず聴診器で呼吸音を聞く |
| 視診 | 口の中の衛生状態観察:残留物はないか 表情に左右差はないか
よだれはないか 頬・舌・唇の動作 |
|
触診 |
舌骨と甲状腺軟骨動き方 |
感染対策
1)肺炎の回復を促す
・口の中、気道を清潔に保つ(口腔ケア・喀痰吸引・体位ドレナージ)
2)摂食・嚥下機能の回復を促す
・嚥下機能の評価(食物形態・姿勢を検討し食事介助を行う)
・摂食ペースの調整
*認知症者は、理解が困難であり、忘れてしまう事が多い
嚥下障害の検査(テスト)
・反復唾液嚥下テスト(repetivive saliva swallowing test:RSST)
・改訂水飲みテスト(modified water swallowingtest:MWST)
・嚥下内視鏡検査(videoendoscopic examination of swallowing:VE)
・嚥下造影検査(videofluorosccopic examination of swallowing:VF)
・認知症者の認知症ステージを把握する
・既往歴の確認と誤嚥の関係を理解する
・通常の全身状態観察と今後予測される事態を理解しておく